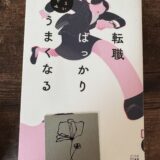SNSで見かけ、図書館で予約した一冊。
くまモンの生みの親、中川政七商店のブランディングも担当されていた著者の水野学さん。
センスとは何か。センスとはどうすれば習得することができるのか、といった内容が詰め込まれている。
具体的にこれをすればいい!というような参考本ではなく著者の実体験を元に「センス」と言われる抽象的なものが解読されており、とても読みやすかったです。
気になった点は以下の通り。
・全ての仕事において「知らない」は不利
・センスとは知識の集積である
・ひらめきを持たずに知識を蓄える
・「他とは全然違うもの」を生み出す前に。手始めに「誰でも見たことがあるもの」という知識を蓄えることが大切。
・一番少ないのは、「誰も見たことがない、あっと驚くヒット企画」。イメージとして2%ほど。
「あまり驚かない、売れない企画」は15%ほど。「あまり驚かないけれど、売れる企画」20%ほど。
一番多いのは「あっと驚く売れない企画」63%ほど。
「誰も見たことがないような、あっと驚く企画を作りたい」と思っている人はたった2%の「あっと驚くヒット企画」にばかり目がいき、全体の63%を占める「あっと驚く売れない企画」には目を瞑っている。
まずは「あっと驚く売れない企画」はコアなターゲットに向けたもの以外、社会に求められないことがほとんど。
現実の厳しさを知ったところで「あまり驚かないけれど売れる企画」に注目するといいでしょう。
過去に存在していたあらゆるものを知識として蓄えておくことが、新たに売れるものを生み出すには必要不可欠。
過去の蓄積、「あっと驚かないもの」を知っていればいるほど、クリエイティブの土壌は広がる。
・センスの最大の敵は思い込み。主観性。思い込みを捨てて客観情報を集めることこそセンスを良くする大切な方法。
・センスのいい家具を選べる人はおそらく、インテリア雑誌を100冊や200冊には軽く目を通している。あるいはお店を回ったり詳しい人に話を聞いてそれに匹敵する情報を得ているはず。
・その人のセンスは感覚ではなく、膨大な知識の集積。センスとはつまり、研鑽によって誰でも手に入れられる能力。
・効率よく知識を増やすテクニック
①王道から解いていく ②今流行しているものを知る ③「共通項」や「一定のルール」がないかを考えてみる
・デザインを構成する要素は ①色 ②文字 ③写真や絵 ④形状 に分けられる。
②文字は歴史的知識が役にたつ。ヨーロッパで作られた書体、アメリカで作られた書体。それぞれに歴史が宿っている。
・「感覚的にこれがいいと思うんです」は禁句。センスが知識の集積である以上、言葉で説明できないアウトプットはあり得ません。
自分のセンスで作り上げたアイデアについて、きちんと言葉で説明し、クライアント・消費者の心の底に眠っている知識と共鳴させる。そのためには知識の精度を高め、アウトプットの精度を高めなければなりません。
・デザインは細部に宿る。ブランドは細部に宿る。
・ありそうでなかったものを作り出すとき、しばしば「差別化」という言葉が使われる。これは「ほんの少しの差」を指すのではないか。ただし「ほんの少し違う」だけではダメでその先に求められるのが「精度」。
・知識を加えて、消費者へのベネフィット(付加価値)とする
とても盛りだくさんな内容でした。
知識を蓄積し、アウトプットの精度を高めていかなければならないというのは、クリエイティブな仕事をされている方でなくても社会人全員に当てはまると思います。
日本のサラリーマンの読書、勉強時間は世界的に見てもとても少ないと言われています。
日常的に勉強、日々のあらゆる場面から学びを得ていくことは生きていく上で不可欠だと再認識しました。
また読み返したくなる一冊でした。
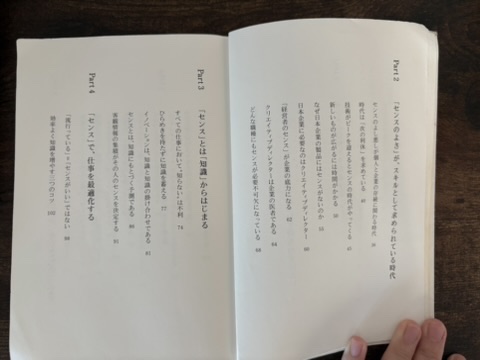
|
|
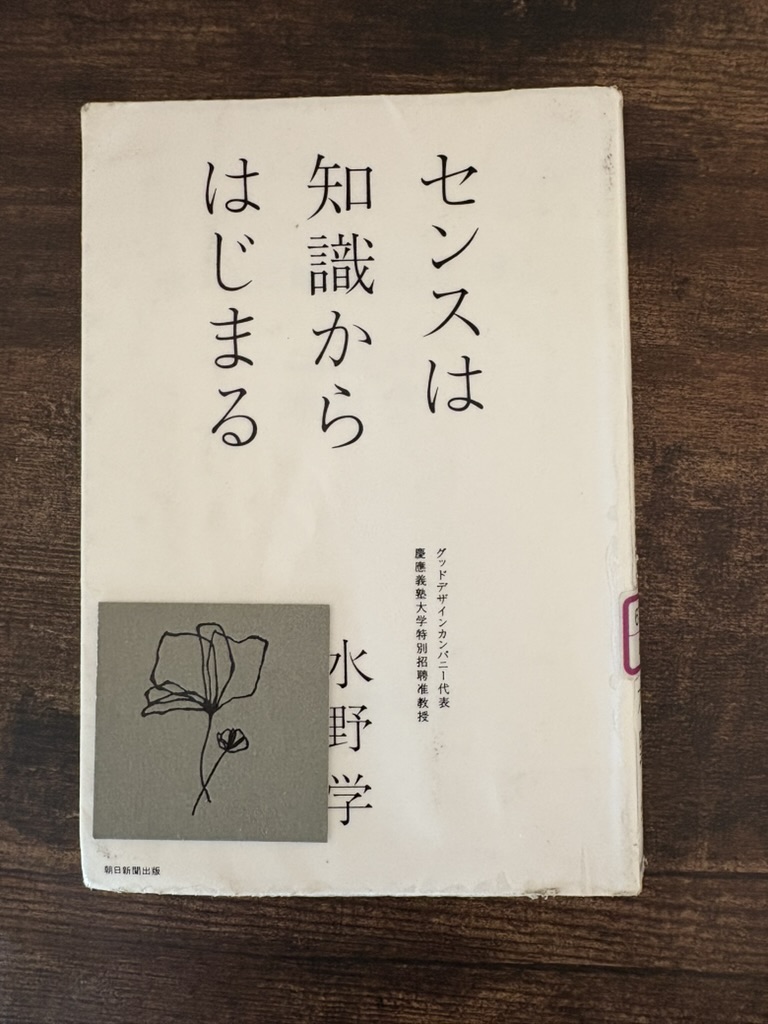

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/495fe435.895b7b72.495fe436.11af10f9/?me_id=1213310&item_id=16865696&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1744%2F9784022511744_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)